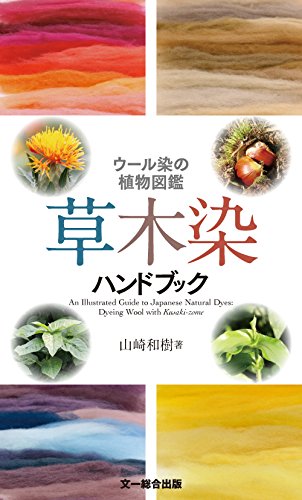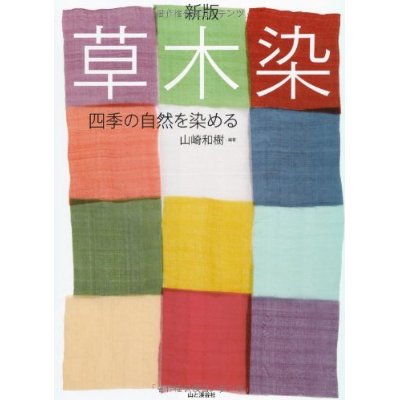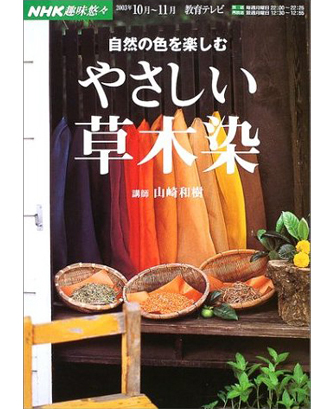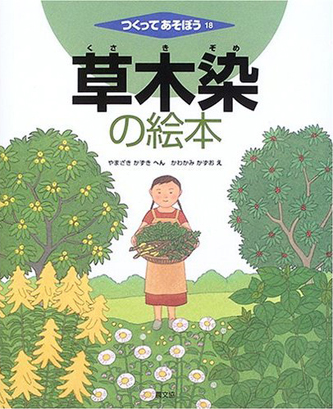草木工房の植物 香椿(チャンチン)、楠(クスノキ)、三葉躑躅(ミツバツツジ)、一輪草(イチリンソウ)

今日の型染クラスの講習会は、1年目の人はスケッチ、墨書きをしました。2年目以降の人はそれぞれ糊置きや型彫り、糊落とし等をしました。

今日は藍と紅花の畑を耕しました。一輪草、山吹、碇草も咲いています。

今日も昨日と同じく、玉繭から袋真綿と角真綿をつくる講座でした。来月はこの真綿から糸を紡ぎます。

今日は、玉繭から袋真綿と角真綿をつくる講座でした。

四川省の漢方薬市場では、紅花、クチナシ、キハダ、ミョウバン石、ビンロウジ、蘇芳、アカネ、紫根、イタドリ、黄連、エンジュなどを発見!! 大満足の一日。

黄色色素を抽出した紅花にアルカリ水を加えて約2時間放置。紅花を絞り、紅色素を抽出。酸で中和して、絹オーガンジを染色。

紅花に水を加えて2時間置いて紅花の黄色色素1番液を抽出。さらに水を加えて一晩置く。明日の紅花染めの準備終了。

ウメ(梅)Prunus mume・バラ科 草木工房の梅を3月3日に撮影。この梅は祖父・山崎斌が植えたもの。 中国原産の落葉低木、古代日本に渡来し、観賞用、果実を食用にするため広く各地で植栽されています。アルミ媒染で赤茶 […]

山地の林の中に生える多年草です。緑色の小さな花を穂状につけます。 染料植物園での説明では「日本最古の染料植物で,飛鳥時代以前から摺り染めに使われた」とありましたが 「染料をとる藍(アイ)や琉球藍(リュウキュウアイ)とよく […]